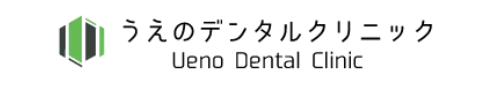虫歯
tooth decay
虫歯はどうしてできるのでしょうか?
むし歯の原因には①細菌(ミュータンス菌)②糖質 ③歯の質 の3つの要素があります。
この3つの要素が重なった時、時間の経過とともにむし歯が発生します。
①細菌(ミュータンス菌)
ミュータンス菌は歯垢(プラーク)となって歯の表面に付着し、糖質から酸を作り出します。その酸が、歯の成分であるカルシウムやリンを溶かして歯をもろくスカスカにしてしまいます。
②糖質
食べ物に含まれている糖質(特に砂糖)は、ミュータンス菌が酸を作る材料に使われます。間食が多い人や、キャンディーやドリンクなど甘いものをよく摂る習慣のある人は、歯の表面が酸にさらされる時間が長いため、むし歯になりやすくなってしまいます。
③歯の質
歯が作られる時の環境の違いやエナメル質や象牙質や唾液の質などで虫歯のなりやすさには個人差があります。特に乳歯や永久歯が生えたばかりの子どもは注意が必要です。
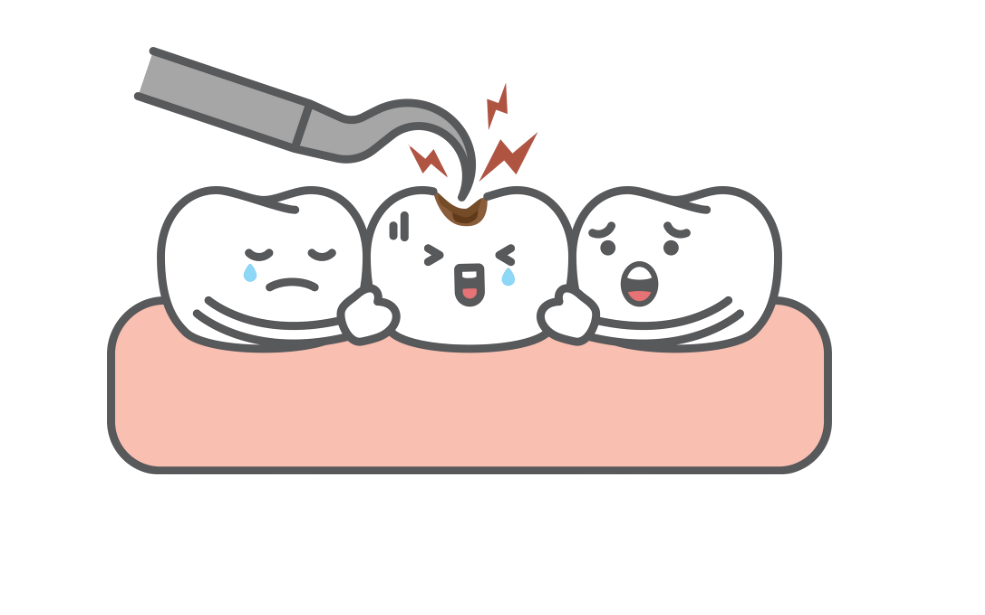
虫歯の進行度について
歯医者さんで虫歯の検査を受けていると「C1(シーワン)」や「C2(シーツー)」という言葉を耳にすることがあるかと思います。これは虫歯の進行度を表す言葉です。Cは虫歯を意味する「caries(カリエス)」の頭文字で、数字が小さいほど進行度が低くなります。それぞれの段階の症状と治療法についてご説明します。

C0 虫歯の前兆
痛みが生じることはなく、歯の表面に白い斑点ができたり歯に透明感がなくなります。この状態であれば、適切なケアを行えば進行を止めることができるため、フッ素塗布や経過観察が選択肢となります。

C1 エナメル質の虫歯
歯の一番外側を覆っているエナメル質だけに虫歯がある状態です。痛みが生じることはなく、虫歯の穴も小さいため、歯を少し削り修復材を詰めることで治療することができます。

C2 象牙質の虫歯
虫歯が少し深くなり、エナメル質の下の象牙質まで虫歯が広がった状態です。痛みを感じることもあります。修復材だけで治療することが難しく、詰め物・被せ物を作らなければならない場合が多くなります。

C3 歯の神経にまで達した虫歯
虫歯の穴が象牙質を超えると、歯の神経と血管で構成されている歯髄(しずい)にまで感染が広がります。 安静時にも歯がジンジンと痛むようになります。感染した歯髄は抜かなければ治すことができません。

C4 ボロボロになった虫歯
歯の頭の部分である歯冠がボロボロに崩壊し、歯の神経も死んでいます。これまで生じていた痛みが嘘のようになくなるため、自然に治ったと勘違いされる方も少なくありません。抜歯が適応され、入れ歯・ブリッジ・インプラントといった補綴治療が必要になります。
虫歯は早期発見が大事です
虫歯の原因や進行状態などについてご説明をさせていただきましたが、虫歯の治療では歯を修復や機能回復をすることはできますが、虫歯のない状態に戻す事はできません。
虫歯を繰り返してしまうと歯を毎回削る事になり歯が小さくなっていってしまいます。 最終的には歯としての機能を果たさなくなってしまい抜歯になってしまいます。
虫歯はゆっくり進行します。 定期的な歯の検診にお越しいただいて、虫歯の前兆(C0)や早期の発見(C1)ができれば、歯を削る事もほとんどなく、生涯ご自身の歯でお食事を楽しめます。
痛みや違和感が出てからでは、虫歯が進行している場合が多くあります。 痛みや違和感などがなくても、歯医者さんを受診してくださいね。